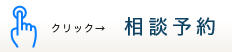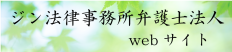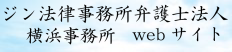よくある質問
熟慮期間とは?
熟慮期間は、相続放棄ができる期間です。
民法915条1項で、相続の承認・放棄は、相続人が相続の開始があったことを知った時から原則として3か月以内になされなければならないとされています。
これが熟慮期間と呼ばれるものです。
熟慮期間の趣旨
熟慮期間内に相続人は相続財産や債務の内容を調査して、承認するか相続放棄をするか決めます。
この熟慮期間がすぎると単純承認したものとみなされます。
相続したものとみなされるのです。つまり、相続する場合には、相続放棄等の動きをしなければ良いことになります。
この3ヶ月の熟慮期間がある趣旨は、相続人の利益の保護と相続債権者の保護を比較衡量したものと言われます。
相続債権者の保護は、相続関係の早期安定の要請でもあります。
最判昭和59年4月27日
この熟慮期間が3ヶ月であることは争えないのですが、これがいつから始まるか、その起算点については多数の裁判例で争われています。
そして、最高裁昭和59年4月27日判決で次のような判断がされました。
民法915条1項本文が相続人に対して3か月の熟慮期間を認めているのは、相続人が相続開始の原因事実及びこれにより相続人となった事実を知れば、通常この期間内に相続財産の有無や状況等を調査することができて、相続の承認・放棄のどちらを選択すべきか判断できると。
「ただ、例外として、相続人が上記各事実を知った場合であっても、その時から3か月以内に限定承認又は放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつこのように信じるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算するのが相当である」
3ヶ月過ぎてから債権者から急に請求を受けた場合の相続人の保護をはかった内容です。
例外的に、債務が全くないと思い込んでいたため相続放棄しなくて大丈夫と考えて3ヶ月が過ぎてしまった場合には、そう思い込んだことにつき過失がないことを条件に、起算日を遺産の認識時又は認識可能時まで遅らせることができるとした判断です。
債権者からの請求
相続人が債権者から請求を受けた時は、遅くともその時から熟慮期間は始まることになります。
裁判例では、債権者から被相続人に対する貸金債権についての承継執行文付金銭消費貸借契約公正証書謄本の送達を受けた時から熟慮期間は始まるとしたものがあります。直接的な請求ではなく、債権の存在を示す書類であれば、債権があることはわかるからです。
債権者からの照会を受けたら、遅くともそこから3ヶ月以内には相続放棄の申述や熟慮期間の伸長などの動きには出ておくべきでしょう。
たとえば、福岡家小倉支審昭和60年2月6日。
債権者から被相続人に対する貸金債権についての承継執行文付金銭消費貸借契約公正証書謄本の送達を受けたのに、相続放棄は8ヶ月後にしたという事例。遅くとも、この送達で、相続すべき消極財産の有無や状況等を確認し得る状態に至ったものと認められるとして、相続放棄の熟慮期間を進行、8ヶ月後の申述は不適法として却下されました。
「遅くともこの送達時において申述人らは相続すべき消極財産の有無、その状況等を認識し得る状態に至ったものと認められる。そうすると、相続放棄の熟慮期間は前記送達日から進行するものと解されるので、それから法定の3ケ月間を徒過した後に申立てられたことの明らかな本件各申述は、いずれも不適法として却下を免れない。」
「自分が相続人ではない」と思っていたら?
仙台高決昭和59年11月9日。
相続人なのに、勘違いして自分が相続人でないと思っていたケース。
その勘違いに気づいてから、熟慮期間はスタートすると判断しました。
相続人となった被相続人の弟妹が、被相続人の配偶者の連れ子が先順位の相続人であると誤信したため、被相続人の死亡を知った時から3か月経過後に相続放棄の申述をした事案。その誤信に気づいた時から民法915条1項所定の熟慮期間を起算すべきとしました。
「認定の事実関係に徴するとき抗告人らがこれに関する親族法・相続法を誤解したことを目して許すべからざるものとするまでの必要はないものと考える。」
しかし、逆の内容の裁判例もあります。
東京高決平成12年10月23日。
父母が離婚。父が親権者になったことで、母とは親子関係がなくなったと勘違いした。
母が死亡。3ヶ月経過した事案で、相続放棄の申述が受理されませんでした。
「抗告人は、被相続人とは親子関係がないと認識しており、自己が相続人であることを確認したのは平成12年8月10日であるから、その日を起算日とするよう主張する。
よって検討するに、相続放棄のための3か月の熟慮期間は、上記のとおり、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知った場合であっても、その時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が上記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」
「しかしながら、抗告人は、被相続人に相続財産が全く存在しないことを信じたのではなく、父母の離婚に際し父が自己の親権者になったことから、母である被相続人との親子関係はなくなったと思い込んだことにより、熟慮期間中に相続放棄の申述をしなかったにすぎないのであるから、本件は、上記熟慮期間の起算日の繰下げが認められる場合には当たらないというべきである。加えて、抗告人は、熟慮期間中に妹のAが相続放棄の手続を進めていることを知りながら、その時点で何の調査もしないまま熟慮期間を徒過してしまったのであるから、熟慮期間内に相続放棄の申述をしなかったことにつき、汲むべき事情を見いだすことはできない。」
被相続人との関係が疎遠な場合
被相続人と同居していれば財産を把握しやすいです。
逆に関係が疎遠な場合には、これを把握しにくく、長期間が経過した後も相続放棄が認められる可能性はかなりあります。
広島高決昭和63年10月28日。
申述人が、被相続人と別居してから死亡まで全く交渉がなかったことや、資産や負債について全く知らされていなかったこと等から、申述人が、被相続人の死亡の事実や自己が相続人となったことを知った後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することは著しく困難として、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認め、相続放棄を有効と判断しています。
「抗告人らは、亡Aの死亡の事実及びこれにより自己が相続人となったことを知った昭和63年1月24日当時、亡Aの相続財産が全く存在しないと信じ、そのためにその時から起算して3か月以内に相続放棄の申述をしなかったものであって、しかも保証協会からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるから、民法915条1項本文の熟慮期間は、抗告人らが保証協会に対する債務の存在を認識した昭和63年6月7日から起算されるものと解すべきであり、したがって、抗告人らが同月20日にした本件相続放棄の申述は、熟慮期間内に適法にされたものであるというべきである。」
逆に、疎遠とは認められない場合には、熟慮期間の繰り下げが認められにくくなります。
大阪地判昭和60年4月11日。
被相続人と同居し、被相続人の死後に、被相続人の経営会社の役員に就任したというケース。
被相続人が積極財産を有していたことを知っていただろうと推認されてしまい、熟慮期間の起算点の繰下げは否定。
「被告1は、被相続人とともに本件契約締結に際し被告会社の原告に対する債務の連帯保証人になり、被相続人死亡後は被告会社の代表取締役に就任して被告会社の経営に当り、被告2、同3も被告会社の取締役に就任していること、被告1らはAの生前からその死亡まで被告会社の本店所在地でもある肩書住所地で同人と同居して生活していたこと、被告1らは被相続人の相続財産である本件土地を同人の死亡後第三者に賃貸したこと、昭和57年7月には本件貸付債権を被担保債権として右土地につき競売開始決定を受けたこと等の事情がうかがわれ、これらの事情を総合すると、被告らはいずれも被相続人の死亡当時同人が被告会社の代表取締役として、積極、消極の財産を有していたことを当然知っていたものと推認される」
さすがに、ここまで事情が揃うと、難しいですね。これだけ読むと、なぜ相続放棄をしたのか疑問を感じる事案です。
不動産などのプラスの財産を認識していた場合
最判の基準からすると、積極的なプラスの財産を認識していれば、熟慮期間はスタートするものとされます。
それに従って、熟慮期間を厳しく認定し、相続放棄を認めない裁判例も多いです。
たとえば高松高決平成13年1月10日。
「抗告人は、被相続人の死亡をその当日に知り、それ以前に被相続人の相続財産として、宅地約68.83平方メートル、建物約56.30平方メートル、預金15万円があることを知っていたといえるから、抗告人は被相続人の死亡の日にその相続財産の一部の存在を認識したものといえる。
そうすると、民法915条1項所定の熟慮期間は、被相続人の死亡の日である平成9年3月6日から3か月であるといえるから、同期間経過後になされた本件相続放棄の申述は不適法である。」
全部、他の相続人が相続するものと思っていた場合
すべて他の相続人が相続するから自分は関係がないと思っていた場合でも、財産等の認識があるとして、熟慮期間はスタートしてしまうでしょう。
たとえば、山形家長井出審平成7年3月14日。
「相続放棄の熟慮期間の起算点を繰り下げることができるのは、相続放棄をしなかったのが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があるため、そのように信じるにつき相当な理由があると認められるときに限定されるものと解される」
「被相続人の遺産はすべて長男が相続するものとされていたため、申述人らは、最初から自己が相続することは考えておらず、相続放棄手続自体も知らなかったことが認められるものの、他方、申述人らは、被相続人に遺産があることを知っていたこと、申述人は被相続人と同居しており、申述人2及び同3は東京都に居住しているが、実家である同申述人1方との往来は保たれていたこと、申述人2は被相続人が急送の役員となっていたことを知っていたこと、申述人らは、遺産である不動産の名義を長男に移転するため、同人の求めに応じ、平成5年1月ころには相続分不存在証明書を作成したことの各事項が認められるのであり、熟慮期間の起算点を繰り下げうる場合に該当しないことは明らかであるといわざるをえない。」
遺産分割に同意している以上、熟慮期間はスタートしてしまうといえます。
これに対抗する理論としては、遺産分割協議自体の効力を消せるような内容でしょうか。
たとえば、錯誤などで遺産分割協議の効力を失わせれば、相続放棄への道が見えてきます。
大阪高決平成10年2月9日。
遺産分割協議をしているので、単純承認になるのではないかという議論がされましたが、これを錯誤で否定。
相続放棄受理の余地があるとして原審に差し戻しています。
「原審は、抗告人らは、本件遺産分割協議により遺産について処分行為をしたもので、これは法定単純承認事由に該当し、本件申述は法定単純承認後の申立であるから、不適法であるとして、前記各申立を却下した。」
「しかし、原審判の判断は是認し得ない。その理由は次のとおりである。
(1)民法915条1項所定の熟慮期間については、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、3か月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信したためであり、かつそのよ
うに信ずるにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算するべきものと解するのが相当である。
(2)本件においては、抗告人らは、平成9年9月29日、公庫から相続債務の請求を受け、Bに事情を確認するまでは、前記認定の多額の相続債務の存在を認識していなかったものと認められ、生前の被相続人と抗告人らの生活状況等によると、抗告人らが右相続債務の存在を認識しなかったことにつき、相当な理由が認められる蓋然性は否定できない。
(3)もっとも、抗告人らは、他の共同相続人との間で本件遺産分割協議をしており、右協議は、抗告人らが相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したもので、相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認事由に該当するというべきである。しかし、抗告人らが前記多額の相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、抗告人らが相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と抗告人らの生活状況、Bら他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある」
他には、遺言があることで自分のところには来ないと思っていた事例で、相続放棄を有効とした裁判例があります。
東京高決平成12年12月7日。
「抗告人は、被相続人が死亡した時点で、その死亡の事実及び抗告人が被相続人の相続人であることを知ったが、被相続人の本件遺言があるため、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じたものであるところ、本件遺言の内容、本件遺言執行者である銀行の抗告人らに対する報告内容等に照らし、抗告人がこのように信じたことについては相当な理由があったものというべきである。」
「抗告人は、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについては相当な理由があったのであるから、抗告人において被相続人の相続開始後所定の熟慮期間内に単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択することはおよそ期待できなかったものであり、被相続人死亡の事実を知ったことによっては、未だ自己のために相続があったことを知ったものとはいえないというべきである。そうすると、抗告人が相続開始時において本件債務等の相続財産が存在することを知っていたとしても、抗告人のした本件申述をもって直ちに同熟慮期間を経過した不適法なものとすることは相当でないといわざるを得ない。なお、抗告人は、後に、相続財産の一部の物件について遺産分割協議書を作成しているが、これは、本件遺言において当然にBへ相続させることとすべき不動産の表示が脱落していたため、本件遺言の趣旨に沿ってこれをBに相続させるためにしたものであり、抗告人において自らが相続し得ることを前提に,Bに相続させる趣旨で遺産分割協議書の作成をしたものではないと認められるから、これをもって単純承認をしたものとみなすことは相当でない」
複数人の相続人と熟慮期間
相続人が数人いるとき、熟慮期間はバラバラに開始し、進行します。
各相続人が自己のために相続が開始したことを知った時から開始します。
相続人全員で進めなければならない限定承認では、この点を注意する必要があります。
熟慮期間の初日は?
熟慮期間のスタートを1日単位で考えなければならない場合、民法140条により初日不算入とされます。
たとえば、死亡と同時に相続開始を知ったという事案の場合、死亡当日は算入せずに、翌日から数えることになります。
熟慮期間と裁判
相続財産に関して裁判が係属している場合、「相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない」(民訴124条3項)とされています。
訴訟手続は中断することになります。
熟慮期間、相続放棄のご相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。